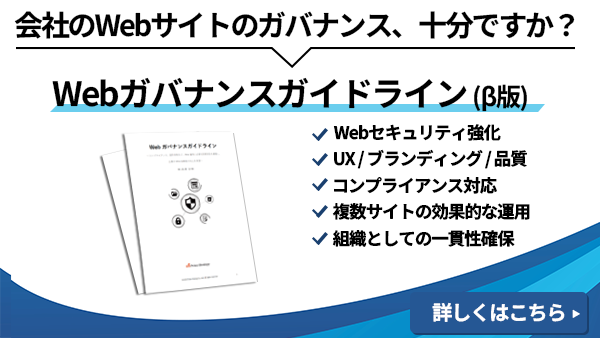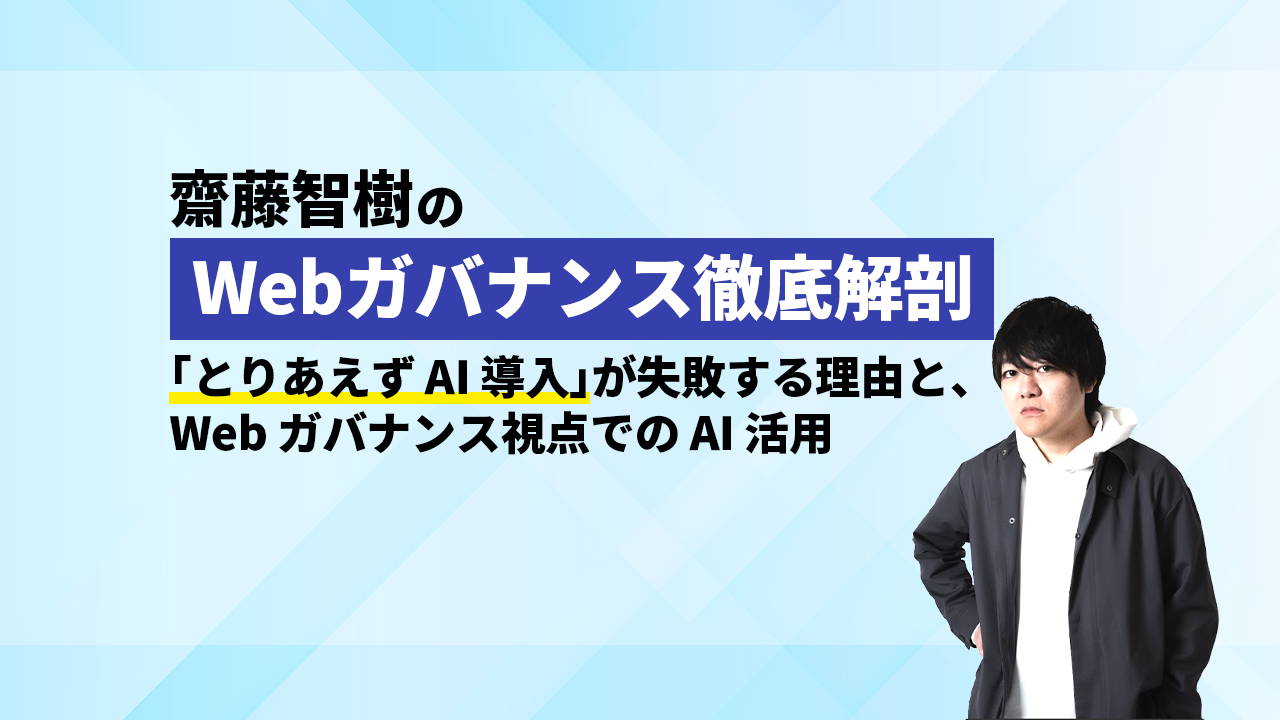
こんにちは、ゼノクリース合同会社 CEO の齋藤です。このコラム記事では、企業の Web ガバナンスや最新情報について紹介しています。
なぜ「とりあえず AI 導入」は失敗するのか?
生成 AI がビジネスに革命をもたらすと言われて久しいですが、実際のところはどうでしょうか。多くの企業が「乗り遅れてはいけない」という焦りから AI 導入に踏み切っていますが、残念ながら「期待した効果が得られなかった」という声をよく耳にします。
典型的な失敗パターン
例えば、企業が顧客対応の効率化を狙って AI チャットボットを導入したとします。
しかし、FAQ が整備されていなかったため、AI は適切な回答ができず、かえって顧客からのクレームが増えてしまいました。
このような失敗には共通のパターンがあります:
| 失敗要因 | よくある事例 |
| 目的の不明確さ | 「AI を使えば何かが良くなるはず」という漠然とした期待だけで導入 |
| データの品質と量の問題 | AI に学習させるデータが古い、間違っている、または量が足りない |
| AI への過度な期待 | AI が人間と同じように考えて判断してくれると思い込む |
1.目的の不明確さ
「AI を使うこと」自体が目的となってしまい、具体的なビジネス課題や目標が曖昧なまま導入を進めてしまうケースです。
例えば、顧客からの問い合わせ対応を効率化するためにチャットボットを導入したものの、FAQ の整備が不十分であったり、AI が対応できない複雑な問い合わせへのエスカレーションフロー(人間のオペレーターに引き継ぎ、それでも解決できなかったらマネージャーに引き継ぎ、など)が確立されていなかったりすると、かえって顧客満足度が低下する結果を招きかねません。
2. データ品質と量の問題
AI は、学習するデータの質と量に大きく依存します。学習に必要なデータが不足していたり、データの品質が低かったり(不正確、偏りがあるなど)すると、AI は適切な判断や生成を行うことができません。
例えば、不正確な顧客データに基づいてパーソナライズされたコンテンツを配信しても、顧客にとっては無関係な情報となり、不快感を与えてしまう可能性があります。
3. AI への過度な期待
AI の得意なこと、苦手なこと、そしてその限界は、そもそもの生成 AI の仕組み(Transformer モデルなど)、によるもののような、タイミングによって変わらないそもそもの特性もあれば、各種モデルの進化具合などのような、時期によるものもあります。
過度な期待を抱いてしまうことは失敗につながります。特に生成 AI の場合、あたかも人間が書いたかのような自然な文章を生成するため、その内容が合っているかのチェックを怠ると、誤情報(ハルシネーション)がそのまま公開されてしまい、企業の信頼性を損なうリスクがあります。
「複雑な要件や、ミスができない要件など、生成 AI で完結させると危険な種類のタスクなのか」それとも、「8 割 9 割正解していれば良いタスクなのか」などの、実現しようとしているタスクの特性を分析することが重要です。
Web ガバナンスが AI 活用の成功の鍵
では、どうすれば AI を上手く活用できるのでしょうか?そのヒントが「Web ガバナンス」にあります。
※ Web ガバナンスとは、簡単に言えば「企業のウェブサイトをきちんと管理・運用するための仕組み」のことです。コンテンツの品質管理(正確で最新の情報を維持)、セキュリティ対策、ブランドイメージの統一、法規制への対応(個人情報保護など)などが含まれます。
なぜ AI 活用に Web ガバナンスが重要なのか
AI は「学習するデータ」次第で性能が大きく変わります。例えば、古い情報や間違った情報を学習した AI は、当然ながら間違った回答をします。
Web ガバナンスがしっかりしていれば、以下のような恩恵を受けられます。
1.質の高いデータを AI に提供できる
- 正確で最新の情報が整理されている
- データが構造化されていて AI が理解しやすい
2.AI のリスクを管理できる
- AI が生成した内容を人間がチェックする体制を確立させておく
- 誤情報や不適切な内容を公開前に防げる(ルールの整備によって)
3.企業ブランドを守れる
- AI の応答が企業のトーンと一致(例えば、カチッとしたイメージなのにチャットボットがカジュアルな口調などの差異)
- 一貫したメッセージを発信(企業の方針やポリシーと異なる内容を生成してしまうなど)
PwC Japan グループの「AI ガバナンス」レポートでも、信頼できる AI の実現には適切な管理体制が不可欠だと指摘されています。(ここでは、Web ガバナンスではなく AI ガバナンスというワードで紹介されています)
今すぐ始められる Web ガバナンスの具体的ステップ
では、具体的に何から始めれば良いのでしょうか?ここでは、Web ガバナンスの具体的なステップの一例を紹介します。
ステップ 1:現状把握
まず自社のデジタル資産を棚卸しすることから始めます。
- Web サイトの一覧化:運用中のサイト、サブドメイン、ランディングページをすべてリストアップ
- コンテンツの監査:古い情報、重複コンテンツ、リンク切れなどをチェック
- 管理体制の確認:誰が何を管理しているか、更新頻度はどれくらいか
ここでは、継続的な体制作りのようなエネルギーが必要な部分は一旦置いておき、とにかく現状の把握に努めます。
ステップ 2:ルール作り
次に、運用ルールを明確にします。
- コンテンツガイドライン:文体、用語統一、画像規格などを文書化
- 更新フロー:誰が作成し、誰が承認し、誰が公開するかを定義
- AI 利用規定:AI で生成したコンテンツのチェック体制、禁止事項を明文化
「継続的にこのルールで行きます!」というように社内で理解を得て浸透させていくのは、かなりエネルギーが必要です。その前段階として、ルール、もしくはルールの叩き台を作ります。
ステップ 3:データ整備
AI が活用しやすいデータ基盤を作ります。
- 構造化データの実装:FAQ、製品情報、会社情報を JSON-LD などで構造化
- タグ付けとカテゴライズ:コンテンツを体系的に分類
- メタデータの整備:各ページの説明、キーワード、更新日を統一管理
この部分は、専門家のサポートが必要な場合もあるかと思います。社内に詳しい方がいらっしゃらない場合は、後述のサービスを利用することも良いかと思います。
ステップ 4:小規模な AI 導入
整備したデータを使って、小さく AI 活用を始めます。
- FAQ チャットボット:よくある質問への自動応答から開始
- コンテンツ生成支援:ブログ記事の下書き作成に AI を活用
- 効果測定:回答精度、利用者満足度、作業時間短縮効果を計測
この部分は、利用者へのアンケートなど実際に費用がかかってしまう部分もあると思うので、状況や規模に合わせて最もカスタマイズされ得るステップだと思います。
ステップ 5:継続的改善
PDCA サイクルを回して行きます。
- 月次レビューで課題を洗い出し
- 四半期ごとに大きな方針を見直し
- 年次で全体戦略を再評価
この段階で、継続的にこのルールで進めていけるように社内に浸透させて行きつつ、PDCA サイクルを回して改善を続けます。
また、この段階にならないと(実際に取り組んでいかないと)分からない課題もあるかと思います。実際、ステップ 1 〜 4 までを行っている期間でおそらく AI のモデルの進化や新しいプロダクトなどの状況の変化もあると思うので、ここは焦らずサイクルを回しながら、その都度課題を見つけて改善していきます。
プライム・ストラテジーのサービスの活用
もちろん、これらすべてを自社だけで行うのは大変です。プライム・ストラテジーでは、各段階に応じたサポートを提供されています。
- CMS/Web プラットフォーム統合サービス: 散在する Web サイトを統合管理し、AI 活用に適した基盤を構築します。WordPress を中心とした効率的な運用体制を実現できます。
- Webガバナンスコンサルティングサービス: Webガバナンスを整備していくための準備から、ガバナンスガイドラインの策定等を伴走支援することで、Webガバナンスの最初の1歩を実現します。
- AI ソリューション: 企業の具体的な課題に合わせて、AI 導入から効果測定まで一貫してサポート。失敗しない AI 活用を実現します。
- MAGATAMA Stack: AI と Web サイトをシームレスに連携させる統合プラットフォーム。データの一元管理と高度な分析が可能になります。(こちらは現在開発中)
まとめ
AI は、現代ビジネスにおいて強力な変革をもたらす「ツール」であることは間違いありません。しかし、その真価を最大限に引き出し、持続的な成果につなげるためには、適切な「羅針盤」としての Web ガバナンスが不可欠です。「とりあえず AI 導入」という安易な発想では、期待通りの効果が得られないばかりか、かえって企業にリスクをもたらす可能性さえあります。
「とりあえず AI 導入」ではなく、まずは Web ガバナンスの確立から始めることで、AI 活用の成功確率は格段に上がります。できることから一歩ずつ始めていきましょう!
【著者】
ゼノクリース合同会社 代表(Web)
齋藤智樹
在学中から高校や予備校、IT 企業に携わり、講師とソフトウェアエンジニアとして活動。
大学卒業後 (2020年4月〜) はフリーランスエンジニアとして活動を始め、以下のような幅広い業務を行う。2021年3月に、業務を拡大させるためにゼノクリース合同会社を設立。スタディングテックの WEB 開発コース主任講師も務める。

プライム・ストラテジーでは、Web担当者様、IT担当者様などの
お役立ち資料やYouTube動画を公開しています。ご興味ある方はぜひご覧ください。